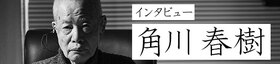長崎県諏訪神社の秋季大祭「長崎くんち」。毎年10月7~9日まで開催される。
前回は祭りや盆踊りに潜む隠れた宗教性を紐解きながら、「日本は無宗教の国ではない」というテーマで筆を進めてみた。この日本列島に住む人々は無意識のうちに宗教的な価値観やものの考えに則って生活をしており、一種の宗教儀式である盆踊りが1年の生活サイクルに当たり前のように組み込まれていること自体、結構すごいことなんじゃないか――そんなことをツラツラと書いてみたわけだ。本稿の後編では祭りと宗教に関するちょっと意外なサンプルを紹介しながら、実はインターナショナルな日本人の信仰心についてご紹介していきたい。
その混血度で群を抜くのが、長崎県長崎市の諏訪神社の祭礼である「長崎くんち」だ。いうまでもなく、江戸時代にはオランダと中国に対する国際貿易港である出島を擁していた長崎は、古くからの混血文化の地。そのため、現在も長崎の祭りは異国情緒を漂わせるものが多い。長崎くんちと同じく、長崎の名物行事として知られる「長崎ハタ揚げ大会」は自作のハタ(長崎では凧揚げの凧をハタと呼ぶ)をブツけ合って勝負を決めるというものだが、このハタはオランダ人と共に出島にやってきたインドネシア人が持ち込んだものといわれている。また、長崎ランタン・フェスティバルは、長崎新地中華街で行われていた「春節祭」(中華圏ではポピュラーな旧正月の祭り)の規模を拡大化させたもの。このように長崎の地に異国の人間が持ち込んだものは数多く、神社の祭礼である長崎くんちにもその影響を見ることができる。
この祭りの象徴ともいえるものに、「龍踊り」というものがある。これは巨大な龍を大人数でクネらせるもので、もともとは唐人たちが春節の祝いのために舞っていたものがオリジナル。にぎやかな銅鑼が鳴り響く囃子も含め、見た感じはほとんど中国の芸能である。そんななかでも混血文化の祭りとしての長崎くんちが凝縮されているのが「阿蘭陀万歳(オランダまんざい)」だ。万歳(萬歳)とは現在の漫才のルーツとも呼べる祝福芸の一種だが、阿蘭陀万歳では同地に漂着した2人のオランダ人が生活のために万歳を披露する様が描かれる。西洋的な格好をした2人のオランダ人(を模した登場人物)に加え、中国風の衣装に身を包んだ唐子たちが舞い、着物姿の女性が日本舞踊を踊るというのだから、その混血具合はかなりのもの。そのうえ、バックで演奏されるのは胡弓がエキゾチックなメロディを奏でる明清楽(みんしんがく)。これは江戸時代、明および清から日本へともたらされた音楽で、当時最先端の「外国音楽」だった。この阿蘭陀万歳が長崎くんちで正式に披露されたのは昭和に入ってからのことだが、このように中国とオランダの文化が入り混じった芸能が一種の「伝統」として現在まで継承されているのだからおもしろい。
長崎くんちが諏訪神社の祭礼として始まったのは1634年(寛永11年)とされる。一説にはキリシタンを一掃し、諏訪神社を中心とするコミュニティを再編しようという目的が当初はあったと言われている。江戸幕府がキリスト教禁止令(禁教令)を発令したのは1612~1613年。それまでの長崎はキリシタンの町だったが、禁止令の発令以降、キリシタンたちにとって苦難の時代が始まる。
そうした中、長崎に住む人々すべてを氏子とし、その祭りとして長崎くんちは始まったとされる。キリシタンたちの団結力を弱め、一掃するための「手段」としての祭り。祭礼の持つ圧倒的なエネルギーがそうやって為政者によって利用されるケースは案外多いが、長崎くんちもそのひとつと言われる。そんな祭りの成り立ちひとつとっても、長崎という土地の複雑な歴史が忍ばれる。
迫害を受けてきたキリシタンたちの苦難を今に伝えるのが、長崎市下黒崎町の枯松神社祭で行われる「枯松神社祭」。この神社が立つ山頂はかつて隠れキリシタンたちが密かに集まり、オラショ(祈り)を捧げる場所だったという。信者たちは明治時代に入って枯松神社を建立、熱心に布教に努めたといわれる日本人指導者バスチャンは、師であるサン・ジワンを祀った。毎年11月に行われる枯松神社祭は、そうした複雑な歴史がそのまま反映されている。最初に行われるのが神父による慰霊ミサ。その後、曹洞宗・天福寺の住職による講演、そして信者によるオラショの奉納が続く。なお、天福寺は江戸時代からキリシタンたちを匿っていたといわれ、当時からの関係性が現在の祭りのなかでも引き継がれているのである。
異国への玄関口であった長崎で長崎くんちや枯松神社祭のような混血文化の祭りが始まり、現在も継承されていることはある種自然なことかもしれない。だが、他の地域の祭りのなかに異国・異人の影が見え隠れすることだってある。

京都・八坂神社の祭礼「祇園祭」。
例えば、日本を代表する祭りともいえる京都「祇園祭」。夏の間、1カ月をかけてさまざまな儀式や演目が行われるが、ハイライトとなるのは宵山・山鉾(山車)の巡行。リズミカルな祇園囃子のビートに合わせ、豪華な山鉾がゆっくりと町中を進んでいく光景は実に勇壮なものである。よく知られているように、この山鉾のなかには異国の装飾品によって飾り立てられているものが少なくない。ホメロスの叙事詩『イーリアス』の一場面を描いたペルシャ製の綴織(つづれおり)、インドやトリキスタン、トルコの絨毯、19世紀初頭にイギリスで作られた「エジプト風景図」など、装飾品のラインナップは実に国際色豊か。
鎖国中にあった江戸時代、京の町民たちは長崎の出島経由で世界各国の装飾品を競い合うように取り寄せ、財力を誇示するために山鉾をデコレートしていったわけだ。日本を代表する祭りである祇園祭の巡行の最中、ピラミッドやラクダが描かれた絨毯が観衆の間を通過していくのは一種異様な迫力があるが、さまざまな混血文化が息づく日本列島を代表する祭りとしては実はふさわしいものともいえるかもしれない。
なお、この祇園祭のルーツをイスラエルのシオン祭りとする説がごく一部に存在する。要するに、日本人とユダヤ人が共通のルーツを持つとする「日ユ同祖論」を証明する際、祇園祭はときたま引き合いに出されるのである。テレビのオカルト番組で物々しく紹介されることもあるこの説に関してはここで深入りすべきではないだろうし、その真偽のほどを検証するだけの知識を僕は持ち合わせていない。
そういえば、青森県三戸郡新郷村(旧・戸来村)にはキリストと弟イスキリのものとされる"墓"がある。皇祖皇太神宮天津教の教祖、竹内巨麿が竹内家の古文書で「ゴルゴタの丘で磔刑になったキリストは密かに日本に渡っていた」とする説を発見、後に新郷村を訪れ、2人の墓を発見したという。戸来(へらい)村という地名は「ヘブライ」を由来とし、同地にはダビデの星を家紋とする家があるといわれ、1936年には「キリストの遺書」まで発見されたらしい。毎年6月にはキリストの慰霊するための「キリスト祭り」が行われるというから、真偽はともかく、かなり気合いの入った話ではある(ちなみに、石川県羽咋郡にはモーゼの墓もあるとか。なんて国だ!)。
ところで、この「キリスト祭り」では"ナニャドヤラ"という歌も歌われる。こちらは古くから青森や岩手で歌われてきた歴史のある盆踊り歌で、民謡研究家の町田嘉章は「日本民謡集」(岩波文庫)のなかで「元歌は一種の呪文的な盲詞を主とする」と書いているほか、かの柳田國男も岩手で出会った"ナニャドヤラ"に興味を持ち、自著「雪国の春」(角川文庫)で「(娘が)男に向かって呼びかけた恋の歌」と持論を述べている。今日、一部で信じられている「"ナニャドヤラ"という言葉をヘブライ語で解釈できる」という説はさすがに眉唾に過ぎるが、歌そのものは東北の奥地らしいディープなフィーリングに溢れたもので、墓のなかに眠るイエス・キリストも思わず踊り出したくなる……?

大阪府の史跡・難波宮跡で開催されるお祭り「四天王寺ワッソ」。
大阪では日本の国際性を感じさせる祭りが行われている。それが難波宮跡で1990年から行われている「四天王寺ワッソ」だ。東アジアの国々から日本に渡来した人々の巡行と、使節団を出迎える日本の偉人たちとの交流催事の再現がメインで、祭りのなかでは「ワッソ」という掛け声が繰り返される。この掛け声について、昨年亡くなった民俗学者、谷川健一は名著「うたと日本人」(講談社現代新書)でこう書いている。
「(ワッショイは)『ワッソー』という朝鮮語に由来すると聞いたことがある。新しい祭りであるが、大阪では四天王寺ワッソという催しがあり、朝鮮人の服装をした人たちが行列を作って練り歩く。ワッソーはもと朝鮮語で『来た』という意味のようであるが、それが祭りのときのかけ声やはやし言葉に変じたと見られる」
もちろん、「ワッショイ=ワッソ」説に対する異論の声もある。だが、古代の時代から東アジアをさまざまな人々が行き来し、民衆レベルでの交流や文化的な影響関係があったことは否定のしようのない事実だ。
例えば、長い歴史を持つ雅楽にしても、そのなかには大陸から伝わった唐楽や半島系の高麗楽が含まれており、現在も雅楽を代表するものとして継承されている。そこからは古代から中世にかけて東アジア一体で活発に行われた文化交流の跡が忍ばれる。また、一般的には「日本古来の楽器」とイメージされることの多い三味線にしても、大陸の三弦が琉球王国に持ち込まれ、それが大阪の堺に渡ったのは16世紀のこと。わずか500年前に輸入された舶来の楽器だったわけだ。日本列島の人々はそうやって他国のものを受け入れ、すでに存在していた他の文化と融合させながら新たなものを生み出してきた。そのクリエイティビティと懐の深さ、異国の文化に対する理解力は大したものだと思う。
日本という列島の古層では異国から伝わってきた多種多様な文化が入り混じっており、日本人である僕らの好奇心もくすぐるエキゾチックな魅力に溢れている。そして、祭りにはそうした日本の特性、音楽と宗教の密接な関係性が凝縮されている。近所で行われている祭りや盆踊りに置き換えても、少しだけ見方を変えるだけでまったく新しい日本の姿が立ち上がってくるかもしれないのだ。こんなにおもしろい国は、なかなかないと僕は思う。
(大石 始)