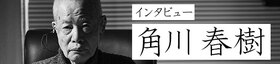法と犯罪と司法から、我が国のウラ側が見えてくる!! 治安悪化の嘘を喝破する希代の法社会学者が語る、警察・検察行政のウラにひそむ真の"意図"──。
今月のニュース
名大女子大生老女を殺害
2014年12月、名古屋大学1年の19歳の女子学生が、自室を訪れた77歳の女性を斧で殴ったのち絞殺。15年1月に愛知県警によって逮捕された。調べに対し女子学生は「子どもの頃から人を殺してみたかった」「高校時代に友人に毒を飲ませた」などと供述している。ただ、こうした親族間以外の殺人が極めてまれであるのは本文で述べられている通りだ。
2015年1月、名古屋大学の女子学生(19)が、宗教の勧誘のためにアパートの自室を訪ねてきた女性(77)を殺害したとして逮捕されました。女子学生は、本誌14年10月号のこの連載でも取り上げた佐世保市の高1女子同級生殺害事件(14年7月発生)の加害生徒と同様に、「子どもの頃から人を殺してみたかった」などと話しているそうです。
このような、なんら罪のない人が唐突に殺されるという痛ましい事件が発生する都度、メディアや国民の間では、「昨今犯罪はどんどん凶悪化している」「だからこそ犯罪被害者を保護し、支援しなければならない」という声が高まります。そして実際そうした世論を受け、99年に始まった司法制度改革の一環として、08年には被害者参加制度が導入され、被害者が裁判に出席して証人尋問や被告人質問等を行えるようになるなどの法整備が進められてきました。
しかしながら、拙著『安全神話崩壊のパラドックス』(岩波書店)をはじめ、私がこれまでたびたび指摘してきた通り、犯罪に関する各種データを眺めてみれば、日本の治安は決して悪化などしておらず、また犯罪も凶悪化していないことは明らかです。刑法犯の認知件数は11年連続で減少し、殺人の認知件数に至っては、ピーク時の1954年に3081件だったのが、2014年には939件と3分の1以下にまで激減し、戦後初めて1000件を下回っている。今や日本の国民にとって犯罪は、自分自身はもちろん身の回りを含めても、“実体験”として見聞きする機会はほとんどないものとなっているのが実状なのです。
結果、犯罪に関する国民の知識やイメージは、メディアの伝える断片的かつ一面的な間接情報のみによって形作られることになる。そして、国民の多くが、いったいどんな人が、どんなケースで犯罪の被害に遭い、その後どんな生活を送るのかという実態を知らないままに、犯罪被害者保護を訴えているわけです。むろんそれでは、実効性のある有意義な議論などできようはずがありません。
では、「犯罪被害者保護」をいう前に、そもそも犯罪被害者とは“誰”なのか? そこで今回は、一般的には身近とはいえないその存在について、関連データや過去の事件を眺めながら、2回に渡ってその内実に迫ってみたいと思います。
はじめに、本稿で扱う“犯罪被害者”という言葉の定義を明確にしておきましょう。ひと口に犯罪被害者といっても、自転車を盗まれた者から何者かに殺された者まで、被害の程度はさまざまであり、それらをひとくくりに論じることは現実に即しているといえないためです。
また、凶悪犯罪だけに話を絞って語るとしても、殺人とそれ以外の犯罪とでは事情が大きく異なります。なぜなら殺人の場合、いうまでもなく被害を受けた当事者は殺されてすでにこの世にいないため、法律上、犯罪被害者というとその遺族も含まれてくるからです。
加えて、強姦の犯罪被害者というのも扱いが難しい。たとえ行為としては同じでも、合意の上での姦通ならば強姦にならないわけですから、裁判においては、行為があったか否かの証明ではなく、合意の有無が焦点になってくることが多い。つまり、被害者自身が加害者と同様に裁かれるわけです。ゆえに、強姦被害者については、権利の擁護からケアに至るまで、他の犯罪の被害者とは分けて考える必要があります。
それらを踏まえて本稿では、犯罪の代名詞的な存在として常々語られながら、実際に体験することはほぼ皆無である“殺人”を取り上げ、その直接の被害者および遺族について詳しく論じることにします。
まず、殺人被害の当事者像について論じてみましょう。実のところその一般的なイメージには、いくつかの大きな誤解が見受けられます。殺人被害の当事者と聞くと多くの人は、ある日街中で通り魔にいきなりナイフで刺殺されるとか、カネ目当てで家に押し入ってきた面識のない男に絞殺されるとかいった“不運な”犠牲者をまず思い浮かべるでしょう。ところが実際には、日本で発生する殺人事件全体からいえば、そうしたケースは極めてまれであるといえます。
『警察白書』(14年版)によると、殺人の被疑者と被害者の関係を見たとき、通り魔や強盗のような面識のないケースはわずか10・3%にすぎません。つまり殺人という犯罪は、9割方顔見知りの間でのみ起こっているわけです。さらにいうと、全体の実に53・5%を親族間の殺人が占めている。その内訳は、配偶者間(内縁の者を含む)が18・0%、親殺しが16・8%、子殺しが11・4%など。その中には、いわゆる心中や嬰児殺がかなりの割合で含まれていることも忘れてはなりません。
要するに、やや皮肉な物言いになりますが、世間の同情を集めてやまない殺人の被害者の“遺族”というのは、その半数以上が、まさにその被害者を殺した加害者本人でもあるというわけです。ですから、単に「犯罪被害者を守れ」と言ってしまうと、親族間で起こることの多い殺人に関していえば、「犯罪被害者(=遺族)すなわち加害者を守れ」と主張していることになってしまう。そうした点だけをとってみても、実状を踏まえず、十把一絡げに犯罪被害者について論じるのがどれだけ無意味なことであるかおわかりいただけるでしょう。
同様に、まったく落ち度がないのに殺されたかわいそうな人、という被害者像も、しばしば現実とはかけ離れてしまうことがあります。なんの責任もないのに殺される“無垢な被害者”というのは、実はかなりレアな存在なのです。ドイツの犯罪学者ハンス・フォン・ヘンティッヒは、48年発表の論文において、犯罪被害の原因は被害者にもあるとする説を唱えました。当然ながらその主張は、被害者に対する偏見やバッシングを助長するものとしてのちに批判を浴びることになるのですが、こと殺人に関していえば、真実の一端をとらえていた面が確かにある。
たとえば、06年に発生した新宿・渋谷エリートバラバラ殺人事件では、夫からのドメスティックバイオレンスから逃れるために一時保護施設に避難した妻が、就寝中の夫を撲殺したとされています。そのように、むしろ加害者側が、それまでの日常においては加害者に虐げられ続けていた弱者であり、だからこその“最終手段”として強者たる相手を殺してしまった、というケースは数え切れないほど存在します。
それが現実であることを裏づけているのが、殺人全体に占める女性加害者の比率に関するデータです。『犯罪白書』(14年版)で入所受刑者人員の罪名別の男女構成を見てみると、刑法犯全体における女子の比率が8・3%であるのに対し、殺人における女子の比率は16・3%でおよそ2倍。放火の12・8%、窃盗の11・7%など、他のどの罪種よりも高くなっています。殺人というものが、ある意味において“弱者の犯罪”であることの何よりの証左といえるでしょう。
このように、殺人という犯罪は、その過半が親族間で発生し、しかも被害者にあまり同情できないケースが少なくない。また、そもそも殺人のほとんどは、怨恨・金目当て・ケンカという3つの要因によって引き起こされる。ゆえに、特に金持ちでもなく、危険を避けてごく無難な社会生活を営む一般の人々は、自分が被害者になったり遺族になったりする可能性をほとんど考慮する必要がない。そうしたことが、殺人の被害者や遺族に対する国民の関心が高まらず、理解がなかなか深まらない一因になったと私は考えています。
ところが、そのような社会に埋もれる存在だった「犯罪被害者」が、1960年代以降の日本の社会構造の変容と、それを受けての国民の意識の変化によって、にわかに表舞台に浮上してきたといったら、皆さんはどう思われるでしょうか? 次回は、そうした社会背景に関する分析を交え、犯罪被害者の遺族についてさらに深く論じたいと思います。
河合幹雄(かわい・みきお)
1960年生まれ。桐蔭横浜大学法学部教授(法社会学)。京都大学大学院法学研究科博士課程修了。社会学の理論を柱に、比較法学的な実証研究、理論的考察を行う。著書『安全神話崩壊のパラドックス』(岩波書店、04年)では、「治安悪化」が誤りであることを指摘して話題となった。その他、『終身刑の死角』(洋泉社新書y、09年)など、多数の著書がある