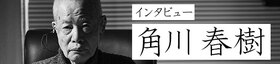――サブカルを中心に社会問題までを幅広く分析するライター・稲田豊史が、映画、小説、マンガ、アニメなどフィクションをテキストに、超絶難解な乙女心を分析。
岡崎京子作品の中では少々神格化されすぎの感もある『リバーズ・エッジ』の実写映画化が、アラフォーサブカルクラスタの間で小規模な話題となっている。鑑賞者の評価としては、『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』並みに賛否真っ二つ(筆者調べ)だが、そこは深掘りすまい。ひとつだけ言うなら、同作の本編部分は、エンドロールで流れる小沢健二(オザケン)の書き下ろし新曲「アルペジオ(きっと魔法のトンネルの先)」を気持ち良く聴くための壮大な前説、超長尺のPVだと考えれば、筆者も含めた全員が幸せになれる。
94年に単行本化された『リバーズ・エッジ』が批評界隈で絶賛を浴びた岡崎京子と90年代の渋谷系音楽シーンに君臨したオザケンは、世代的にも嗜好的にもファンのかぶりが多い。というわけで良い機会なので、今回はアラフォー都市型文化系女子の一翼を担う「オザケン好き女子」について考えてみたい。
オザケン好き女子の属性としてよく挙げられるのが、「元オリーブ少女」だ。オザケンは94年から97年にかけてマガジンハウス発行の雑誌「Olive(オリーブ)」にエッセイを連載していたが、その時期に10代後半~20代前半だった女性読者に占めるオザケンファン率は高い。彼女たちは都会的で知的でファッショニスタでサブカル(棒読み)なライフスタイルに憧れを抱き、教室の「普通のコ」たちとは一線を画したハイなセンスをもって音楽も映画も文学も読み解ける私(悦!)、という自負を燃料に90年代を駆け抜けた。オザケンファンと90’sオリーブ少女が完全に一致しているわけではないが、ベン図的にはそれなりに重なっている。
引用を多用するオザケンの楽曲や、平易なリリックに潜む深い文学性は、知的でありたいサブカル大好きっ娘たちの「読み解き欲」を大いに刺激した。また、当時の小沢が「王子様」と呼ばれたゆえんでもある、中性的で薄口醤油なご尊顔、照れもなく恋人を「仔猫ちゃん」と呼んでしまうキラキラ感、「東大卒」「叔父が世界的指揮者の小澤征爾」といったサラブレッドスペックなどが、プライド高めで自意識青天井90’sガールたちのハートにクリティカルヒットしたのは、想像に難くない。小室哲哉だのエイベックスだのビーイングだのといったJなPOPが「普通のコ」たちに幅を利かせていた90年代中盤、「シブヤ系」「ブンガク臭」が、彼女たちの選民意識をどれほど刺激&鼓舞したことか。
オザケンの音楽的功績などはググるなりwikiるなりしていただくとして、注目したいのはブレイク以降の経歴だ。彼は90年代末に突如生活の拠点を米国に移して以降、メディア露出を極度に避け、日本の音楽シーンから思い切り距離を置いて身を隠すようになる。やがて環境問題関連のフィールドワークに身を染めて南米などを行脚しはじめると、以前のポップでラブリーな作風からはかけ離れた、資本主義社会を批判する意識の高い寓話テキストを意欲的に発信して、かつてのファンを少なからず戸惑わせた。10年代以降は徐々に日本のメディアにも姿を見せはじめ、2014年には16年ぶりにテレビ出演を果たし、現在に至る。つまり元オリーブ少女世代である現在のアラフォーオザケン好きは、「教祖が民の前からお隠れあそばした」という信仰上の大受難を10年単位で乗り切った、筋金入りの信者だ。
ただ、下界再降臨後の教祖オザケンの活動をきちんと追うには、少々骨が折れる。このSNS全盛の「拡散してナンボ」時代に、出される情報も本人の露出も小出しであり、あらゆるメッセージはテクニカルな暗喩に満ち、“プロ”による読み解きを必要とするからだ。
なぜ彼女たちはいまだにオザケンを崇めるのか。それは、彼が90年代とは別の意味で、今でもやんごとなき「王子様」を実践しているからだろう。「ファンとアーティストの距離が詰まること、即ち絶対善」な10年代においても、オザケンはファン(下民)と容易に繋がらない場所に、意図的に身を置いている。彼個人はツイッターもインスタグラムもやっておらず、下民の使うSNSなどというツール程度では彼に言葉を届けることはできない。
小沢のオフィシャルサイト「ひふみよ」も、かなり一方的な情報提供と美意識の置き場所としてしか機能していない。「ひふみよ」にはコメント欄もなければ、ツイッター窓もなし。多くのテキストコンテンツは「縦書き文章」を「画像ベース」で読み進めることが暗に推奨されており、昨今のネット流儀(などという下民が求めるリーダビリティ)など気にも留めないサディスティックな貴族っぷりが痛快だ。そこには、「この形式以外で伝える気はさらさらないし、僕の主張については1mmも意見されたくはないんだ」と嫌味なくサラッと言ってしまえる、まことにナチュラルボーン王子様の気概が健在である。フォロワーをひとりでも多く増やそうと躍起になってクソリプにも寛容な心で返信する下民ブロガーのせせこましさなど、歯牙にもかけないノーブルさ。むしろ清々しい。
ネットとSNSが発達した10年代、アーティストは言わばUGC(User Generated Contents/ユーザー生成コンテンツ)化した。動画共有サイトと同じく、アーティストはユーザーの反応や顔色をSNS等で漏れなく受け取り、時に直接対話し、彼らのニーズにしたがって自分を作り変える。しかしオザケンは、下民がお手軽な手段などでコミットできない、UGCからは最も遠い場所にいる。そこが尊い王子様たるゆえんであり、いまだ根強いファンがついている最大の理由ではないだろうか。ファンはオザケンの「絶対不可侵性」に、歓びとともに跪いている。
現在のインターネット世界では、下民どもの集合知(という名の衆愚活動)によってカリスマたりとも一瞬で消費&スポイルされてしまうが、オザケンは汚辱にまみれたネット世界の必要悪的機能美なんぞに頼ることなく、一貫してピュアな活動を貫いており、その輝きは(下民たちのクソリプによって)曇ることはない。そう考えると、10数年間という「お隠れ」は、下民が巣食う日本の芸能界やマスメディアという俗世の汚染から逃れるための適切な避難措置であり、彼が王子様として「徳」を積むために必要な天界行脚ターンだったのかもしれないと思えてくる。
オザケンというコンテンツは他に類を見ないほど不親切で、不可侵で、コミットしにくい。でも、ファンにとってはそこがいい。そこが、在り難い。オリーブ少女時代から20年以上、世のありとあらゆるコンテンツを鬼のように消費し、UGCの栄枯盛衰を目撃し、コンテンツ消費の速度と劣化ぶりに幾度も失望してきたアラフォー都市型文化系女子たちが今でも、否、今だからこそオザケンに心酔するのは、彼が下民の消費などによって劣化しないコンテンツだからだ。下民の吐く臭い息などに染まらない絶対的聖性を有しているからだ。
彼女たちが再降臨後のオザケンに頭を垂れて手を合わせ、御託宣に耳をそばだてるのは、単に「昔好きだったから」が理由ではない。彼が今でも尊い「王子様」だからである。映画『リバーズ・エッジ』を観て90’s青春時代のノスタルジーに浸るオジサンたちとは次元が違う。女は現在に信仰を見いだし、男は過去に嗚咽する生き物なのだ。
稲田豊史(いなだ・とよし)
編集者/ライター。キネマ旬報社を経てフリー。『セーラームーン世代の社会論』『ドラがたり のび太系男子と藤子・F・不二雄の時代』(共に単著)、『ヤンキーマンガガイドブック』(企画・編集)、『押井言論 2012-2015』(編集/押井守・著)、『ヤンキー経済 消費の主役・新保守層の正体』(構成/原田曜平・著)など。編集担当書籍に『団地団 ~ベランダから見渡す映画論~』(大山顕、佐藤大、速水健朗・著)、『全方位型お笑いマガジン「コメ旬」』(ラリー遠田:責任編集)がある。
『リバーズ・エッジ』
2018年・日、監督:行定勲。川沿いの高校を舞台に、いじめ、LGBT、摂食障害、ドラッグ、死体、自殺といった90’s若者文化全部入りのダークな青春ドラマが展開する。基本的には原作に忠実だが、劇中で監督が突然登場人物(を演じる役者)に「あなたにとって愛ってなんですか?」などとインタビューするメタな作りは結構アレ。