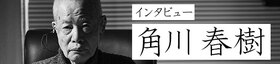――上京して数十年、すっかり大坂人としての魂から乖離してしまった町田康が、大坂のソウルフードと向き合い、魂の回復を図る!
photo Machida Ko
白味噌を入れすぎたためゲサゲサになってしまった土手焼きを前に私は方途に暮れていた。足りなければ足せばよいが、入れすぎたものを引くことはできない。というか、一度、入れてしまったら自ら責任を取らなければならない。私の知り合いで泥酔して入れてしまったため、意に染まぬ結婚をした者がある。私はその男をあざ笑ったが、いまはこの男と同じ立場に立ってしまっている。
さあ、どうしたものか。どうもこうもない。入れてしまったものを取り出すことができない以上、水で薄めるより他はない。もちろん、それが下策中の下策であることは承知している。薄めたところでいったん生じたえぐみがなくなるわけではない。えぐみはえぐみとして残る。そして、いい感じのゲル状態だったのが、なんだかしゃぶしゃぶした、でも一部には半ばはヘドロ、半ばはコレステロールのような嫌な塊が、汚らしく淀んで、食欲というものを根底から否定する。また、それ以外は一定のバランスを保っていた、酒、出汁、味醂、砂糖などは大量に注入された水によって薄まり、バランスは崩壊するだろう。
ということがわかっているにもかかわらず水を入れなければならないのは悲しいことだった。入れすぎた。それを解消するために、また、余計なものを入れる。失敗して駄目になったものは実はなにをやってもよくならない。いったん駄目になったら打てるのは悪手のみなのだ。だったら、悪手なんだったら打たなければよいではないか、てなものであるが、打たなければもっと駄目になる。打ったら打ったで駄目になる。だって悪手だからね。
それならばなにもしないで座して死をまてばよいのか。それはそうなのだけれども、なかなかそうできないのが人間だ。百万の敵が上陸してきた。それに比べて我が方は二百。装備は貧弱で弾薬も残り少ない。だからといって戦わない訳にはいかない。全滅覚悟で引き金を引き続けるしかないのだ。
そんなことで私は方形の鉄板に水を入れ、火を少し強くした。
といってしかし、方形の鉄板の立ち上がりは僅僅一・四センチであり、一度に入れられるのはせいぜい五十竓かそこいらである。ということは入れすぎた白味噌に起因するえぐみがあまり薄まらないということである。というか、実際の話が、水を入れて再び中央の、瓦斯火が当たっているあたりがぐつぐついいだした頃合いで、匙にとって舐めてみたが、臆病になりそうなえぐみはちっとも薄まっていなかった。
それでも頑張って少しずつ水を足し続けた。そして、ただ水を足したばかりではない、水を足すと同時に、砂糖、味醂、酒も足していった。鍋のなかにおける白味噌の比率を少しでも下げたいと思ってのことだった。足しながら、日銀の買いオペとはこういうことなのだろうか、なんて思ったのは味見のしすぎで脳がかなり悪くなったからだろう。
まともな人間でいるためには少し口直しが必要だ。そう思って、一合入の紙パックとは別に、一升瓶を持ってきて湯呑みにどくどく注いで飲んだ。飲みながら水を足し続けた。味醂も砂糖も足した。酒は紙パックが空しくなったので一升瓶から足した。
鍋ばかりではなく自分自身にも酒を足した。湯呑みにどくどく注いで。
そうでもしないとやりきれなかった。だってそうだろう、いまこの時間、多くの人は何をしているだろうか。そう。社会で一生懸命働いている。ある人は自動車の部品を作り、ある人は田を耕し、ある人は国の政策を決定するなどしている。何百億という金の取引をしている人もいるだろうし、誰かのために重い荷物を運んでいる人もいるだろう。
それに引き比べて、俺は、この俺はいったいなにをやっているのか。一日中、薄暗い台所に立って、土手焼きの鍋をかき回している。馬鹿だよ、馬鹿。もっと他にやることがないのだろうか。もっと有意義なこと、誰かの役に立つことができないのだろうか。ははは。できねんだよ、俺はよ。できねぇから、こうやって土手焼きの鍋をかき回してんだよ。その土手焼きだって失敗してんだよ。酒でも飲まないとやってらんねぇんだよ、文句あったら、こいっ。
と、虚空を睨め付けて怒鳴り、水を足し、酒、味醂、砂糖を足し続けた。自分には湯呑に注いだ酒を足し続けた。湯呑の表面にはハローキティーちゃんという猫の化け物が描いてあった。ハローキティーちゃんがそんな私をじっと見つめていた。ハロー、キチちゃん。
どこで意識が途切れたのかわからない、気がつくと台所とひとつながりになった居間で横になっていた。頭の芯の辺りが、どんよりした熱を帯びているようだった。甘い匂いがリビングに漂っていた。あっ、鍋。慌てて起き上がると、「やあ、起きたのかい」と、男の声、見やると台所と居間の境のあたりに折鴨ちゃんが立っていた。