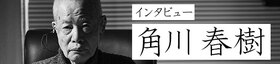──既得権益がはびこり、レッドオーシャンが広がる批評界よ、さようなら!ジェノサイズの後にひらける、新世界がここにある!
『明日、ママがいない オリジナルサウンドトラック』(バップ)
日本テレビ系ドラマ『明日、ママがいない』が、いわゆる児童養護施設の描写を巡って批判を浴び、ファンタジー路線への変更を余儀なくされた。作中の児童養護施設の現実とは乖離した描写が視聴者の誤解を呼び、児童の通う小中学校でのいじめを誘発するというのが批判の主な内容だ。そもそも「いじめ」の発生しやすい現在の学校教育の在り方(学級という流動性の低いコミュニティへの適応を児童に1年から2年単位で余儀なくさせる)の改善でこうした問題には対処するのが正統であり、ドラマ番組への批判は的外れであると思う。
さて、思わぬ「炎上」で話題を集めている同作だが、僕の興味はまったく別のところにある。それは野島伸司という作家のゆくえについての興味だ。同作には「脚本監修:野島伸司」「脚本:松田沙也」とクレジットされている。野島の関与がどの程度あるのかはよくわからないが、テーマといいドラマツルギーといいキャラクター造形といい、かつての(90年代の)野島作品(特に『家なき子』)を強く想起させる、もっと言ってしまえばセルフ・パロディ感のある作品に(今のところ)仕上がっている。第一話で三上博史が杖をついて出てきた瞬間に、懐かしさのあまり苦笑してしまった野島ファンも多いはずだ(僕もそのひとりだ)。
これは野島自身による自己批評的なセルフ・パロディなのだろうか。それとも若いスタッフによる「野島的なもの」への批評的アプローチなのだろうか。
考えてみれば、この10年は野島伸司という作家が時代とズレていく自分と向き合ってきた10年だったとも言えるはずだ。象徴的なのは『ラブシャッフル』の終盤の展開だろう。同作は、高級タワーマンションの最上階に住む6人の男女とその周辺の人々が、恋人交換のゲームを行うという物語だ。台詞回しも演出も、キャラクター造形も意図的に80年代後半のそれに近づけてあり、普通に観ればイタくて仕方がない作品だ。しかし注意深く観ていると、同作は野島が「80年代的なもの」の復権を訴えるべく、あえてその時代のテイストを前面化させてあることがわかる。そう、野島は当時(09年)という時代にバブル的なものの再召喚が必要だと訴えていたのだ。そして最終回、玉木宏演じる主人公はなんと、衆議院議員に立候補して時代をバブル期に戻せと演説する。まるで「間違っているのは自分じゃない、世界のほうだ」といわんばかりの展開だ。