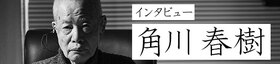SNS隆盛の昨今、「承認」や「リクエスト」なるメールを経て、我々はたやすくつながるようになった。だが、ちょっと待て。それってホントの友だちか? ネットワーク時代に問う、有厚無厚な人間関係――。
『小田嶋隆のコラム道』
小学生に友だちの数を尋ねると、たぶん曖昧な答えが返ってくる。100人と言うかもしれない。30人と答えるかもしれない。どっちにしても、彼らは自分の友だちの数を正確に数えることができない。というのも、小学生にとって、友だちは、自分の周囲にいる同年齢の子どもたちのほとんどすべてを含む概念で、口をきいたことのない隣のクラスの児童であっても、互いに顔を見知っていれば友だちの数に算入しているかもしれないからだ。それほど彼らにとって、友だちの垣根は低い。
内気な子どもの場合、日常的に交際している子どもの数は、実際にはそんなに多くない。ひとりか2人ということもある。が、本人の意識の中では、友だちはずっと多い。ひとクラスが30人であるとするなら、おそらく、20人までは友だちだと思っている。
小学生にとっての「友だち」の定義は、現実に行き来のある相手に限られるわけではない。同じクラスにいて、なんとなく親しみを感じているだけでも、彼らにとっては友だちということになる。このことは、年齢の低い子どもにとっては、「自分が友だちの中にいる」ことがとりわけ重要だということでもある。もしかしたら、彼らにとって、「自分」というのは、単独で生きて動いている存在ではなくて、ある程度の数の友だちの中において初めて機能する部品のようなものなのかもしれない。
何年か前、何かの席で、夢の話が出た。
「夢の中の映像に自分は映っているのか」
というのが、その時の主たる話題だった。
結論からいえば、普通、夢は、自分視点の映像として提供される。ということは、夢の中では、「自分」は、「カメラアイ」そのもので、だから、基本的に、被写体として撮影されることはない。ということは、夢の中の絵には、登場人物としての自分は出てこないことになる。
が、私を含めた何人かは、「子どもの時の自分」が映像として登場する場合があることを主張した。
そう。おっさんになってしまった現在の自分の姿を夢の中で見た記憶はないのだが、子どもの頃の自分は、時々自分の夢の中に出てきている気がする。これは、かなり不思議なことだが、本当の話なのだ。
私の場合「映っている」子どもは、意識として「本人」でもある。ともあれ、夢の中で、私は小学生の子どもに戻っており、そういう時、私は映像を伴った姿で、自分の意識の中に登場しているのである。
「それ、お前がどうかしてるだけだぞ」という意見もあった。
そうなのかもしれない。
が、憶断すればだが、ある年齢までの子どもの自意識は、単独の人間としてではなくて、自分を取り巻く環境をまるごとひとつのセットとして含んでいる。つまり、彼らは、「自分」という存在を、内側からではなくて、外側のカメラから見ている気分で暮らしているのである。
自他が未分化だという言い方はあんまりに乱暴かもしれない。が、人が子どもであるということは、「友だちに囲まれている環境」と「自分が存在している」ということが、ほぼ等価であるような一時期を指しているはずなのだ。
関連して、つい最近読んだ記事の話をする。
「洋ゲー」と呼ばれる、アメリカ製のゲームは、主人公視点のカメラで描写される場合が多く、対して日本製のゲームは主人公を含めた場面をカメラマンが撮影した設定の画像が多いという話だ。
この違いは、洋画と日本画の違いにも及ぶ。洋画では、描き手の視点は固定されており、であるから、描かれる絵画は、必然的に、その確固たる視点から切り取った瞬間としてカンバスに固定される。
ひるがえって、日本画では、視点は描く対象に沿って自在に動く。遠景にある富士にも、手前の道を歩く人物にも等しく焦点が当たっている。それゆえ、遠近法は成立しにくい。絵巻物や屏風絵のような画面では、描き手の視点は、空間的のみならず時間的な意味でも「移動」する。すなわち、ひとりの人間の一生や、ある物語の進行を1枚の画面の中に納めてしまう。
この話は、たぶんツイッターで誰かの書き込みからリンクした先で読んだものだ。メルマガの記事だったのか、ブログのエントリーだったのか、あるいは何かの書籍の書評だったのかもしれない。
いくつかの検索ワードで探したのだが、オリジナルが見つからなかった。で、申し訳ないのだが、記憶から引用させてもらっている。
私がこの話を引用したのは、順序としては、ウェブで読んだこの洋ゲーの視点の話が、いつだったか自分たちが話題にしていた夢の話に似ていることに気づいたからで、それらの「視点」の違いには、もしかして、我々の「自意識」の問題が隠れているのではなかろうかと考えたからだ。
大げさな仮説を振り回すつもりはない。
ただ、この連載の中で話をすすめるに当たって、私は、子どもの自意識が、外界すなわち「友だち」に依存しているという話をしておきたかったのである。
我々は、子ども時代の映像を「夢」として記憶し、それに「友だち」というタグをつけて処理している。そういう意味でいえば、「友だち」は、単に親しく付き合っている人間というよりは、我々を少年時代に戻すためのスイッチなのかもしれない。
大人である我々の自意識は、個人的で、内的で、固定的なものだ。私は私であり、私以外のものではあり得ない。が、子どもたちにとって、「ボク」なり「あたし」は友だちとセットになっている。そこのところが、「友だち」という現象を解く鍵なのだと私は考えている。まあ、解いたところで何がどうなるというものでもないのかもしれないが。
さて、小学生にとってクラスメートの半数以上は友だちだった。
しかしそれは、年齢とともに減っていく。
中学生になると、クラスの中で頻繁に行き来する仲間の数は5人ぐらいに減少する。もちろん、ほかの生徒とも一応の付き合いはあるし、頻繁に付き合うメンバーは、時とともに変遷したり入れ替わったりする。が、トータルの人数は増えない。親しい仲間が2人増えれば、それまで親しかった2人ほどとは、なんとなく疎遠になる。つまり、中学生ぐらいになると、友だちとより「深く」付き合うようになるわけで、そういう「腹を割って話せる」友だちは、どうしても数が限られる。
これが高校生になると、クラスのうちの半分は、はなから没交渉になる。ファッションや、話し方や、成績や人生についての取り組み方のいずれかがそうさせるのだが、理由がなんであれ、話の糸口が見つからないタイプの人間は、徐々に増える。と、友だちの数はさらに減る。こういうふうに見ていくと、子どもが大人になるということは、そのまま友だちを失っていく過程であったりする。
で、大人になると、友だちは、事実上消滅する。
無論、かつて友だちだった人間が友だちでなくなるわけではない。そういう意味では友だちはいる。
ただ、高校時代や大学生だった頃に親しく付き合っていた「親友」と呼べる人間と、現実に会う機会が持てるのかというと、それは別の話になる。物理的に住所が離れてしまっている場合もあるし、そうでなくても、仕事の忙しさや、環境の違いで、対面の機会は、物理的に制限される。
もちろん、親友は、何年かに一度でも、会う機会を作れば、たちまち親友に戻ることができる。
しかしながら、親友に戻ることは、単に昔に戻っているということであって、だから、現状をわかち合っているのではない。腹を割った話は、親友だからこそ、むしろ口に出せないのかもしれない。早い話が、借金の話はできない。
「親友の借金を断る人間は親友とは呼べない」という話は、逆方向から見れば、
「親友に借金を申し込む人間は親友とは呼べない」
ということでもあるわけで、結局のところ、絵に描いた友情は自縄自縛に陥る。
職場の同僚や、行きつけの飲み屋で顔を合わせる知り合いの中に、親しい人間がいないわけではない。が、彼らが「友だち」なのかというと、ちょっと違う。なにより利害関係や上下関係が介在している。
ということはつまり、社会に出た人間は、原則として新しい友だちを作れなくなるということだ。
友だちは、学校という施設の副産物だったのかもしれない。
次回は、何を書こう。気が遠くなってきた。
小田嶋 隆(おだじま・たかし)
1956年、東京赤羽生まれ。早稲田大学卒業後、食品メーカーに入社。営業マンを経てテクニカルライターに。コラムニストとして30年、今でも多数の媒体に寄稿している。近著に『小田嶋隆のコラム道』(ミシマ社)、『もっと地雷を踏む勇気 ~わが炎上の日々』(技術評論社)など。
[近況]
年始に高校の同窓会があったのだが、フェイスブックの話になった。我々の世代はアカウントはもっているけど活用していない人が多い。自分も今年はフェイスブックを立ち上げようかな……と考えている。